※ この記事は、KIESS MailNews 2016年2月号に掲載したものです。
◇◇◇◇◇◇◇◇
このレポートは昨年12月の土曜倶楽部でお話しさせて頂いたことをベースとしています。話のきっかけは「未来世代の権利地球倫理の先覚者、J-Y・クストー」という本を読んだことでした。子供の頃「カリプソ号の冒険」(タイトルはあやふやです)というテレビシリーズを見て、バチスカーフに乗り込んで海に潜るクストー船長に憧れていた私は、何となく本を買って読むことにしました。そこで知ったのが、カリプソ号を降りた後のクストー船長(その頃は敬意をこめて「提督」と呼ばれていたそうです)が、亡くなるその時まで「未来世代の権利」のための活動をしていたということでした。そしてクストー船長のこの活動に哲学的なバックボーンを与えていたのがフランスの医師であり哲学者でもあったジャン・アンビュルジェでした。
倫理的動機付けの類型
もう15年ほど前になるのですが、当時カリフォルニア大学のサンフランシスコ校で哲学の先生をしていた有坂陽子さんに教わったところによると、欧米の哲学的伝統では人間の倫理的動機付けには次の3つの類型があるそうです。
- 功利主義的アプローチ
良い結果をもたらす行為が正しい行為である(良いことは正しいことである) - 義務に基づくアプローチ
正しい原則に従って行為するのは良いことである(正しいことは良いことである) - 人格に基づくアプローチ
ある行為を行うかどうかは、その行為(或いは不行為)が自分自身の人格を高めることになるのか、それとも貶めることになるのかによって判断する
これらとは別に東洋には「中庸の徳」と呼ばれる考え方もあります。これは何事においても「極端を避け、中庸を旨とせよ」という教えで、「薬も飲みすぎれば毒となる」というように、正しく見えることでも度を越せば悪となる、だから中庸を旨とせよと戒めているのだと思います。欧米の哲学的伝統に基づく3類型に東洋の伝統である「中庸の徳」を加え、これを「バランスに基づくアプローチ」と名付けるとすると、人間の倫理的動機付けには少なくとも「功利主義的アプローチ」、「義務に基づくアプローチ」、「人格に基づくアプローチ」、「バランスに基づくアプローチ」の4つがあることになります。
ここで問題にすべきなのは、どのアプローチが一番正しいか(或いは優れているか)ということではありません。それぞれの人にとって大事なのは、自分はどのアプローチによる説明が最も納得がいくか、考えてみることなのだと思います。
例えば「功利主義的アプローチ」で考える人の場合には、「この先100年間を考えたとき、このまま地球温暖化が進んだ場合に起こる環境被害の総額よりも、温暖化を防止するために必要とされる費用の方が少ない。だから温暖化対策を進めるべきである」と説得されたとしたら、多分すぐに納得するでしょう。また、「義務に基づくアプローチ」をとり、「公平」を正義の原則と考えている人の場合には、「将来世代の人たちが現代世代と同じようなそ・・・・こそこの環境を享受できないのは不公平であり、正義の原則に反する。だから環境を守るべきである」と説得されたら、割とあっさり納得するのではないかと思います。
個体論と全体論
人間の世界観は大きく「個体論」と「全体論」に分けて捉えることができます。個体論というのは「全体は部分の合計以上のものではなく、実在するのは個々の存在であり、全体は部分から説明できる」とする考え方です。これに対し全体論の方は、「全体は部分の合計以上のものであるとともに、より実在的なのは全体であり、個々の要素(個体)は全体の中でそれが果たしている機能と切り離しては理解できない」と考えています。
近代社会では、個々の存在を実在的と考える「個体論」あるいは「要素還元主義」の世界観が主流の座を占めてきました。このことは自然科学に限らず、政治や経済などの社会科学においても同様でした。例えば、国家の正当性を基礎づける理論としての社会契約説では、個人が集まって契約を結ぶことにより社会が生まれたと考えていますが、このことは、社会が生まれる前に契約を結ぶことのできる自由で独立の個人が存在することを前提としています。考えてみればおかしな話なのですが、この前提が疑問視されなかったということは、近代においては個体論の世界観が特に意識にも上らない程の「当たり前」だったのだと思います。革命後のフランスのように個体論を前提とした社会契約説に基づく社会では、当然ながら個人の自由が重視され、それを守るための個人の権利(人権)が尊重されることになります。個々の人間を権利の主体と考える「個体論的倫理」(近代社会の倫理)においては、個人の権利を守ることが社会の倫理的・道徳的目標となります。そして、この延長線上で環境倫理を考えると、自然界の個々の命を権利の主体と考え、その権利を守ることが新たな倫理的・道徳的目標となるでしょう。
しかし、西欧の歴史に限定したとしても、人間は常にそのように考えてきたわけではありません。古代ギリシャでは、ポリス(都市国家)なしには人間存在は考えられなかったそうで、ポリスに所属しない人間は人間以下の存在とされ、また、実際にポリスの外で生きていくことは不可能に近かったといいます。古代ギリシャでは、人間はポリスのために生き、また、ポリスのために死にました。そこでは、個々の人間よりも全体としてのポリスの方がより実在的なものと考えられていたのです。ペルシャ戦争の際に、レオニダス王に率いられ、ギリシャ連合軍の一翼として戦争に参加した300名のスパルタ軍は、テルモピレイの戦いで数万のペルシャ軍を相手に戦い全滅しました。この時なぜ全滅したのかというと、全員が死ぬまで戦い、1人でも多くのペルシャ兵を倒せば、それだけスパルタの町に辿り着くペルシャ軍の数が減ると考え、退却せずに戦い続けたからだというのです。テルモピレイの古戦場跡の石碑には「異邦人よ、ラケダイモンの人々に告げよ、我らここに眠ると、彼らの掟に忠実に」1)と刻まれているそうですが、ここには全体としてのポリスのために生きた古代スパルタ人の倫理観が表れていると思います(ラケダイモン人というのは、スパルタに住む貴族、平民、奴隷のうち、奴隷を除く人たちのことです)。このような全体の存続を優先する全体主義的な社会においては、全体の存続と繁栄に貢献することが個々の人間に課せられる倫理的・道徳的目標となります。この枠組みの延長線上で環境倫理を考えると、自然においても個々の命ではなく、全体としての生態系を存続させることが倫理的・道徳的目標となるでしょう。
環境倫理のマトリックス
環境倫理というのは、環境を守るべきであるとして、なぜ環境を守るべきなのか、その根拠を説明するものです。これまでになされた環境倫理の主張は、倫理的動機付けの4類型と世界観の2類型からなるマトリックスに整理することが出来ます(表1参照)。
表1:環境倫理のマトリックス
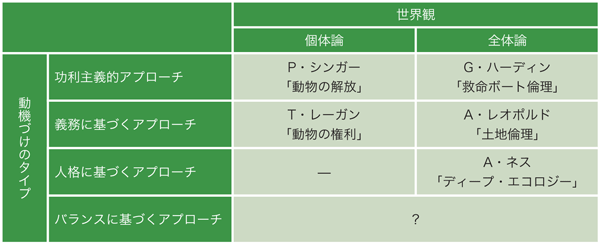
「個体論×功利主義的アプローチ」に該当するのが「動物の解放」を訴えたピーター・シンガーの主張です。シンガーは人間が平等であることの基礎が知性や能力の同等性にあるとする考え方を批判し、これに利益に対する平等な配慮というものを対置しました。そして、平等に考慮されるべき利害の基準を苦痛に置き、苦痛を感じる可能性のある動物も人間と同等に扱うべきとしました。シンガーは、この観点から動物実験や食料としての動物の利用に反対し、ベジタリアンになることを提唱しました。「我々の倫理的責任は苦痛の総量を最小化することである」としたシンガーの考えは、倫理に対する功利主義的アプローチの一つといえます。
次に、「個体論×義務に基づくアプローチ」に該当するのが「本来価値」という観点から動物の権利を論じたトム・レーガンの主張です。「本来価値」とは、何か(例えば人間)の役に立つということとは関係無しに、それ自体として本来的に持っている価値のことです。レーガンは、「本来価値」を持つものには権利があり、人間の側に義務を生じさせると論じました。この際レーガンは、「生命体」であることを「本来価値」を持つものの基準としたのですが、レーガンのいう「生命体」とは、簡単に言えば、それ自身の利害を持つものということです。無生物である石には、それ自身の利害はありませんが、生物であれば、たとえ原始的な微生物であったとしても、生き延びることは「良い」ことであり、寿命を全うする前に死ぬことは「悪い」ことであるというように、それ自身の利害を持っているといえます。
シンガーやレーガンに始まる「動物の権利」に関する議論は、動物虐待の防止や家畜の飼育状況の改善にはそれなりの効果を発揮しました。しかし、野生生物の絶滅防止に関してはあまり効果的ではありませんでした。過去には、乱獲による野生生物絶滅の事例も多数あったのですが、今日における野生生物絶滅の主な原因は生息地の減少です。このため、これ以上の生物多様性減少を食い止めるためには、生息地の保護あるいは生態系の保護といった視点が不可欠といえます。しかし、個々の生物の命を守ることに焦点を当てた「動物の権利論」からは、それ自体は生物ではない生息地や生態系を保護することの直接的論拠は見出し難かったのです。
「土地倫理」(Land Ethics)を提唱したアルド・レオポルドの主張は、その批判者に従えば「全体論×義務に基づくアプローチ」に該当するといえます。米国の国有林を管理する森林官であったアルド・レオポルドは、従来の倫理が機能していた共同体という概念の枠を、自然の総体としての「土地」にまで拡大することが進化の道筋であるとして、「土地」という生命圏共同体全体の安定や美観の保護を重視する全体論的な観点に立った倫理である「土地倫理」を提唱しました。レオポルドの主張の要点は次のようなものです。
人間を取り巻く環境のうち、個人、社会に次いで第三の要素である土地(land)にまで倫理則の範囲を拡張することは、生態学的に見て必然的なことである。土地倫理とは、要するに、この共同体という概念の枠を、土壌、水、植物、動物、つまりこれらを総称した土地にまで拡大した場合の倫理をさす。倫理観の進歩のためには、適切な土地利用のあり方を単なる経済的な問題ととらえる考えを捨てることである。ひとつひとつの問題点を検討する際に、経済的に好都合かという観点ばかりから見ず、倫理的、美的観点から見ても、妥当であるかどうかを調べてみることだ。物事は、生物共同体の全体性、安定性、美観を保つものであれば妥当だし、そうでない場合は間違っているのだ、と考えることである。2)
レオポルドの主張は、倫理的共同体の範囲を土地にまで拡大するという以上に、個体論から全体論への視点の転換を伴っていました。レオポルドの「土地倫理」に表れているような全体論的倫理は、生態系の保護や生物多様性の保護には有用なものの見方ではありますが、現実社会の中でそれを実践的判断の拠りどころとするには様々な困難があります。典型的には、部分としての人間の利益と全体としての生態系の利益が対立した場合です。このとき、人間の利益に優先権を認めてしまうと、全体論的倫理は無意味になってしまいます。しかし、生態系の利益に優先権を認めることも多くの困難を生じさせます。例えば、生態系保護のため立ち退きを迫られたとしても、個人の権利という観点からそれを拒否することはできません。また、地球生態系保護のために人間の数を減らすという方策も正当とみなさざるを得ません。更には、全体論を人間社会に適用すると、全体の利益の名の下に個人を犠牲にする全体主義社会となる恐れもあります。「動物の権利論」を展開したトム・レーガンは、レオポルドの主張を「環境ファシズム」であるとして、次のように批判しました。
権利を基礎とする環境倫理学を発展させることの困難さとその含意の中には道徳的な権利の持つ個体主義的な性質と、自然についてのより全体論的な見方を調和させることも含まれる。アルド・レオポルドはこの後者の傾向を持つ典型である。この見方には、「生命共同体の統合性、安定性、美観」の名のもとに、個体はより大きな生物の善のために犠牲に供されうるという明瞭な視点が言外に含まれている。どのようにしたら個人の権利の概念が、まさに「環境ファシズム」と呼びうる考え方の中に、どのように居場所を見いだすことができるのか、理解しがたいことである。3)
「個体論×義務に基づくアプローチ」という枠組みで環境倫理を探求しているトム・レーガンが全体論を批判しているのと同様に、「苦痛の最小化」という「個体論×功利主義的アプローチ」をとるピーター・シンガーも全体論を拒否しています。これは、「功利主義的アプローチ」や「義務に基づくアプローチ」に「全体論」を組み合わせると、その論理的帰結として「環境ファシズム」と呼ばれるような全体主義なることが避けられないからだと思われます。環境倫理を探求する上での課題は、持続可能でかつ人間として生きるに値する社会の倫理を見いだすことにあります。ここで生きるに値するとは、自由、平等、人間の尊厳など、これまで大切にしてきた価値を完全には放棄しないことを意味します。持続性と基本的人権を両立させる道はあるのでしょうか。
レオポルドの弁護のために書き添えさせていただくと、彼は次のようにも述べています。
土地に対する愛情、尊敬や感嘆の念を持たずに、さらにはその価値を高く評価する気持ちがなくて、土地に対する倫理的関係がありえようとは、ぼくにはとても考えられない。なお、ここでいう「価値」とは、むろん単なる経済的価値よりも広い意味での価値である。つまり、哲学的な意味での価値を、ぼくは言っているのだ。4)
上の一節は、土地に対する愛情、尊敬や感嘆の念を持ち、それを高く評価する気持ちを持つように「我々の人間性を高めること」が、全体論的倫理としての土地倫理の前提であると理解することができます。そうであるならば、環境倫理の探求において、レオポルドは「人格に基づくアプローチ」を採っていたことになります。持続性のためには全体論的見方が必要であり、かつ「環境ファシズム」を避けたいのであれば、「人格に基づくアプローチ」を採ることが残された道なのかもしれません。
意識的かどうかは分かりませんが、「全体論×人格に基づくアプローチ」という組み合わせになっているのが、ディープ・エコロジーの提唱者であり、ナチのノルウェー占領に非暴力の抵抗を行ったアルネ・ネスの思想です。ネスのエコロジー哲学においては、自己実現という概念が重要な位置を占めています。「今日では、自己実現、自己成就といった語は、常に生涯にわたる利己的欲求を満たす努力に結びついたかたちで使われている」5)とネスは言います。利己的欲求を満たすということに問題が多いとしても、人間に利己的欲求があるのも事実であり、ネスはそれを出発点とします。利己主義の反対に利他主義がありますが、利他主義には他者の利益のために自らの利益を犠牲にするという暗黙の前提があります。この場合、自らの利益を犠牲にする動機は主に義務感から生じ、自分を愛するのと同じように他者を愛さなければならないと説くことになります。しかしながら、人間が単なる義務感や道徳心から他者を愛することのできる程度はたかがしれており、それが十分に機能するのなら、遠の昔に戦争はなくなっていたはずだとネスは言います。「人生の初期において、社会的“自己”が十分に育つと、人間は大きなケーキを独り占めにしたいとは思わず、友達や身近にいる人々とケーキを分かち合いたいと思うようになる。こうなると、これらの人々の喜びの中に自らの喜びを、失意の中に自らの失意を見出すまでに、他者を自己と同一視するようになる。全ての生命存在と自己を同一視することができるまでに自己を拡大することができれば(エコロジカルな自己が十分に育てば)、自然を守ることは自分自身を守ることと見なされるようになる。そうすれば、義務感からではなく、人間の本心からの行為が“自ずから”環境倫理に即したものとなる」6)。これがネスの説く、自己拡大を通じた環境倫理への道です。
順番的には少々変になってしまいましたが、「全体論×功利主義的アプローチ」になっているのがギャレット・ハーディンの「救命ボート倫理」です。救命ボート倫理は負傷者選別の考え方を持続性問題に適用したものといえます。負傷者選別というのは、戦場で負傷兵を次の3つに分類することです。
- 治療を受けても受けなくても死んでしまうであろう負傷兵
- 治療を受けても受けなくても助かるであろう負傷兵
- 適切な治療を受けた場合にのみ救われ得る負傷兵
医療資源の乏しい戦場では、3.に分類される負傷兵のみを治療し、それ以外は治療をしません。理由は、戦場では負傷者の数に対して医師や医薬品などの医療資源が不足するため、全ての負傷者に治療を施すことが不可能な場合があり、そういう状況では、3.に分類される負傷兵に医療資源を集中して治療を施すことが、結果として最も多くの兵士の命を救うことになるからです。
この負傷者選別の考え方を持続性問題に応用すると、世界の国々を次の3つに分類することができます。
- 今から対策を行っても持続可能にはなり得ない国(人口過剰で外国からの食糧援助に頼っている貧しい途上国)
- 対策を行わなくても現状で既に持続可能である国(ブータンなど、現代文明の影響をあまり受けていない途上国がこれに当たるかもしれません。)
- 今から対策を行えば持続可能になり得る国(アメリカなどの豊かな先進国)
負傷者選別に倣えば、持続性問題への対応に利用できる資源は限られているので、対策は3.に分類される国にのみ集中し、それ以外の国は放って置くということになります。このため、ハーディンは「アメリカは自国の生き残りだけを考えるべきであり、貧しい途上国に食糧援助などをすべきでない」と主張したのです。
この先、地球環境問題が深刻化したとき、先進国が「救命ボート倫理」に従った選択をする可能性は十分に考えられます。ただし、そうなった時には、負傷者選別では、負傷の程度以外は負傷者間に特に違いはありませんが、持続性問題の場合には、先進国こそが地球環境問題を引き起こした張本人であることを忘れない方がいいと思います。
表1の「バランスに基づくアプローチ」のところは、左右がつなげてあります。これは個体論的倫理と全体論的倫理のバランスを取ることも「バランスに基づくアプローチ」に期待される役割のような気もするからです。中が「?」なのは、実は私自身が「バランスに基づくアプローチ」がどのようなものか、よく分かっていないからです。効率性と安定性というようなトレードオフ関係にあるもののバランスについては、例えば効率性を横軸、安定性を縦軸にとり、両者の関係を示す曲線を引き、曲線から縦軸と横軸に下した垂線が作る四角形の面積が最大になるところが最適バランスだというように、何となくイメージすることができます。3次元の場合には、3要素の関係を示す曲面上の点が作る直方体の体積を最大化するといったところでしょうか。しかし、バランスを取るべき要素が4つ以上になったらどうすればよいのでしょうか。一昔前のCPUには浮動小数点計算ユニット付のものと、そうでないものがありましたが、どうやら私の脳みそには「多次元処理ユニット」が付いていないようで、4次元以上のバランスとなると、どう考えてよいやらさっぱりイメージが浮かびません。この辺の解説については「多次元処理ユニット」をお持ちの内藤先生(当NPO代表)にお願いできればと思います。
人間と自然
人間と自然の関係を考えるとき、人間が自然から生まれたものであり、かつては「自然の一部であった」ということに関してはほとんどの人が同意するものと思います。生物種としてのヒトが、地球における生物進化の産物であることは間違いないからです。もし意見が分かれるとしたら、それは今日現在においても「自然の一部である」と言えるかという点でしょう。この点に関しては、「人間圏」という概念を用いて地球環境問題の本質を説明する松井孝典氏の見解が参考になります。惑星を研究する天文学者である松井氏の見解は次のようなものです。
- 現在の地球システムは、地圏、気圏、水圏、生物圏、人間圏という5つのサブシステムから成ると捉えることができる。
- 最初期の地球は、全てが溶けた灼熱の塊だった。
- 冷えるに従って、地球はまず地圏と気圏に分かれた。
- 更に冷えると、大気中の水蒸気が雨となって地上に降り注ぎ、水圏がうまれた。
- 地球が更に冷えると、生物が誕生し、やがて生物圏を形成するようになった。
- 農耕を基盤とする都市文明の誕生とともに、地球の第5の圏域としての人間圏がうまれた。
- 地球システムの中で、人間圏が大きくなりすぎたこと、これが今日の地球環境問題の根本原因である。
人類の誕生は700万年前に遡るといわれますが、その歴史の大半において人類は地球の生物圏の一員でした。しかし、約5000年前に人間が都市と農地からなる人工の世界としての文明を成立させたことによって、生物圏から独自の圏域としての人間圏が分化しました。この枠組みに従うと、「地球システム全体=自然」とすれば、今も「人間は自然の一部である」ということになりますが、「生物圏=自然」とすれば、都市文明の成立以降については、「人間は自然の一部ではない」ということになります。
人間が自然の一部であるのか、ないのかは、それだけを考えても答えは出ないように思います。ここでの考えるべきポイントは、人間と自然の関係について、どのような認識が一貫性のある環境倫理の根拠を提供し得るのか、という点にあります。
因みに私自身は、松井氏の枠組みを拝借して、人間圏=人工生態系、それ以外の圏域を全部合わせて自然生態系とし、自然生態系(自然)とそれとは異なるものになってしまった人工生態系(人間)を永続的に共存させること、それが持続可能社会づくりの目標であると考えてきました。
世代間倫理
「自然の生存権」と並ぶ環境倫理のもう一つの主要論点が「世代間倫理」です。世代間倫理を最初に主張したのはドイツ生まれのユダヤ人哲学者・神学者のハンス・ヨナスでした。彼は主要著作である「責任という原理」において、従来の倫理では科学技術文明が生み出した新しい状況に対応できないとして世代間倫理の必要性を訴えました。以下はヨナスからの引用です。
人間は大地を掘り返し、鳥、魚、獣を取り、家畜を支配する。しかし、人間は自然の自己回復力を破壊することはできなかったし、また人間自身が死を免れられないという限界を背負っていた。ところが技術的行為の範囲が拡大した結果、行為の直接的な結果だけを評価する従来の倫理学が無効になってしまった。人間の行為が、自然の秩序に永続的な損害を与えないか、同世代人の範囲を超えて未来の人間に影響を与えないか。そういうことが問われるようになった。しかし、こうした吟味に耐えるためには、人間は道徳的意志を持つだけではなくて、知識を持たなくてはならない。人間の行為の本性が変わったので、地球が壊れやすくなった。人間は「地球上の生物圏全体」を、責任の対象としなくてはならない。しかも個々の行為とその結果ではなく、「因果系列の累積的な性格」を考慮に入れて、科学技術の世界変革を評価しなくてはならない。知ることが新しい義務となる。技術が累積的になり、人工環境が拡張され、拡張が自己目的化されると、個別的な行為ではなくて、生産という全体的な行為と政治が道徳性の領域となる。
人工領域は島ではなくなり、自然領域が島となり、世界そのものが滅びる可能性が発生している。世界に人間が存続するという世代間の義務が発生する。カントの「定言命法」が要求するような無矛盾性は、世代間倫理の尺度にならない。新しい命法は「汝の行為のもたらす因果的結果が、地球上に真に人間の名に値する生命が永続することと折り合うように行為せよ」と命ずる。技術が累積して理論的な極限問題に現実性が与えられるようになる。たとえば「地球上に何が生息すべきで、何が生息すべきでないか」というような巨大な規模の問題が現実的な意味を持つ。遠い未来への倫理学が要求されると、代議制度のもとで誰が未来を代弁するのかという難問が生まれるが、どのような価値の知識が重用かという問題に帰着する。技術の集団的、累積的な歩みのもたらすこの新しい可能性が新しい倫理を必要としている。7)
映画「ヒトラー最期の12日間」の終わりに、主人公でヒトラーの秘書であったトラウデル・ユンゲ本人が出てきて語る場面があります。そこで彼女はナチによるユダヤ人虐殺について、「私たちドイツ人は知らなかったと言ってきた。しかし、それは言い訳でしかない。私たちは知らなかったのではない。知ろうとしなかったのだ。」と言っています。これは原発問題など、現在の問題にも当てはまります。「知ることが新しい義務となる」というヨナスの主張には大いに同感です。
しかし、世代間倫理が必要になったのは、本当にヨナスの言うように技術が進歩した結果なのでしょうか。そうだとすると、文明崩壊が起こって技術が産業革命前の水準に戻ってしまった場合には、世代間倫理はいらないということになってしまいます。古代文明やイースター島においても次世代の生存を危うくするような環境破壊は起きており、「技術進歩の結果、世代間倫理が必要になった」というヨナスの主張には、今一つしっくりこない部分もあります。
アンビュルジェの思想
環境倫理の主な論点は、自然の生存権、世代間倫理、地球全体主義(個体論的倫理と全体論的倫理の調整)の3つと言われています。アンビュルジェの思想の画期的な点は、「反自然的権利は反自然的義務を伴う」という思考のアクロバットとでも言えるような発想の転換によって、自然の生存権と世代間倫理に一貫性のある根拠を与えると共に、個体論的倫理と全体論的倫理の対立を吹き飛ばしてしまったことにあります。長くなりますが、以下が1992年11月の第1回世界科学ジャーナリスト会議の基調講演でクストーが語ったアンビュルジェの思想です。
これから話すことをよく聴いてください。世界のすべての人々、富める者も、貧しい者も、飢えている者も。われわれは皆、誇るべきなのです。生来の法則にあえて挑んだ一つの種に属していることを。
この独創的な考えは、初めて最近の国連のスピーチで披露したのですが、フランスの科学アカデミー会長、ジャン・アンビュルジェ教授が、死の数カ月前に私に教えてくれたものです。これはわれわれのエコロジーと環境保護の観念に革命をもたらすかもしれません。アンビュルジェは極めて最近のできごとであるホモ・サピエンスの到来について語ったのです。ホモ・サピエンスは、軟体動物の頂にはタコが、花の世界では蘭が君臨するように、脊椎動物の頂に座す逆説的な存在です。30億年以上をかけて、生命は極めて単純な水中の単細胞生物からまことに複雑な植物・動物へと進化しました。われわれの祖先は300万年前に現れ、生存するだけでも厳しい時期を過ごしました。デズモンド・モリスはこの初期の人間存在を「裸のサル(the naked ape)」と呼んでいます。つまり攻撃する武器も防御のすべも持たず(殻も、牙も、爪もない)、しかもその敵よりも速く走れない存在だということです。それは「犠牲」となるべき存在であり、火を使うようになり、初期の道具を刻むまでは、おそらく生き延びるのに大変な隘路をたどったことでしょう。
自然は永い進化の歴史を通してうまく機能してきました。しかし生命を花開かせ多様化させる責めを負ったそのメカニズムは、残酷さと不公平に彩られたものでした。自然の中では、個体は常に種の生存のために犠牲にされます。無情なジャングルの法則の下、人という犠牲者は自らの存在の不安を感じていたことでしょう。しかし、人は、共同体をつくるやいなや、そしてすべての自然の危険を遠のけたと感じるやいなや、自然と離婚し、自らの法則を発令した、というのです。アンビュルジェは書いています。われわれ人間は個人を尊重したいという。傲慢にも病気を拒否する。早死にを拒否する。自然淘汰も拒否する。自然淘汰とは数知れぬ生き物の中で、まさに奇跡的な生息数の均衡を保証してきたものなのに、それを拒否する。われわれは正義を求める。実際は生命の物語は個々の機会の不均衡の上に成り立っているのに、正義を求める、というのです。
この自然的なるもの、標準となっていたものとの契約破棄は、ごく最近のことなのです。たかだか百世紀くらいのものでしょう。そして、それがおそらく道徳の起源となったものなのです。「人間の出現と共に、その時初めて精霊が息吹く、-それは生来の生物的法則に対する反抗の息吹だった。この反乱こそ人間の運命の本質なのだ。それが人間の名誉なのだ。それは人生に意味を与えるのだ」とアンビュルジェは書いています。続いて「しかし明白なのは、深刻なリスクを背負わないで生命の規範を拒否することはできないということだ。一番顕著な例はわれわれの作りだした人口のアンバランスだ。衛生と医療は、自然の生物学的状況をわれわれがいみじくも拒否したことの、まさしくその表れだが、それにより寿命はほぼ3倍に伸び、資源が限られたこの惑星で、人口は驚くほどの速さで増加し、今も増加し続けている」。彼によれば、ほとんどすべての社会的害悪、飢餓・貧富のショッキングな格差、砂漠化、生物多様性の減少、遺伝する汚染物質の増加、そしてこの地球の温暖化でさえ人口爆発に由来しているのです。
だからこの人口爆発は、われわれの創りだした反自然的な一連の価値観に由来するのです。すなわち寛容、連帯、そして従来の諸悪に対して初めて医学的に勝利を収めたことに対する誇り、こうしたことがその論理的対応すなわちカウンターパートである産児制限にたどりつくまで、長い間、熱烈に支持されてきました。このパートとカウンターパートの間の共時性の欠如のために、われわれはこの革新的なコース、つまり無情な自然の掟をわれわれ自身の理想である公平・友愛・正義に置き換えることが、新しい義務と危険さを伴うという、そのことをなかなか理解できなかったのです。自然の犠牲者から一転、われわれは厳しい自然の保護者にならねばならなかったのです。われわれ自身がジャングルの法則を拒否することによって、われわれは、周囲の動植物の王国がそれなくしては生き延びられないジャングルの法則を常に享受できるよう、保障する責任を負うことになったのです。
われわれは、この最近の自然との離婚が不可逆的なことをまだ十分認識していません。われわれの祖先たちが、ずっと前に橋を燃やしてしまい、もはや自然に帰ることはできないのです。
このことは現代人に途方もない重荷を負わすことになります。生物学的に受け入れることができ、同時に自分の道徳的野心を満足させるような行動を一気に発明せねばならなくなったのです。二百年前、最初の人権宣言の中に、我々の新しい倫理は見事に描かれました。しかし人権宣言は自然の権利ではないのです。この宣言は単に、われわれが闘ってきた高価な戦いに対するご褒美の前触れにすぎませんでした。その戦いとは、30億年も生きとし生けるものを支配してきた法則との闘いであり、たかだか1万年前にわれわれが受け入れがたいと判断したものとの闘いだったのです!この歴史的文書が言及せず、そこに欠けているもの、それはわれわれがこの線を維持するには、一連の未来世代の権利を扱う必要があるということ、また権利は自動的に義務を伴っていることです。また反自然的権利は反自然的義務を伴う、ということも。これらの新しい義務のいくつかは民主主義世界では達成されました。例えば奴隷制の廃棄、戦犯を裁いたニュールンベルク裁判、人種差別に対する大きな抗議、赤十字の創設等です。しかし進歩は、その結果が意識されることなく、同時に一つの小競り合いを引き起こしました。もしわれわれの危うい行動の成功を願うなら、われわれは全人類をわれわれの大冒険に参加するよう説得せねばなりません。そして早急に、恵まれない人々を更に貧しくするのに直接作用している人口爆発を制御しなくてはなりません。さもなくば恨みは蔓延し、憎しみに変わり、数億人を巻き込むおぞましい大量殺戮が起こることが避けられなくなるでありましょう。8)
以上を私なりに要約すると次のようになります。
- あるとき、人は共同体を作ると自らの法則を発令し、ジャングルの法則(自然淘汰による適者生存)を拒否した。
- しかし、野生の生物はジャングルの法則なしには存続できない。
- このため、ジャングルの法則を拒否した人間は、周囲の自然がジャングルの法則を享受できるよう保障する義務を負う。(自然の生存権)
- 野生生物の種の存続はジャングルの法則が保障しているが、ジャングルの法則を拒否した人間は、自ら種の存続に責任を負わねばならない。(世代間倫理)
- 自由、平等などの人権は人間が発令した反自然的権利であり、反自然的権利は自動的に反自然的義務を伴う。(個体論と全体論の対立解消)
このアンビュルジェの思想がクストーにとって画期的だったのと同じように、私にとっても画期的でした。その理由は私が自分を「全体論×義務に基づくアプローチ」のタイプと考えていたからです。「温暖化対策をしないよりも、した方が得だから」という説明には納得できるところもありますが、人を殺してはいけない理由について、「その方が得だから」と言われても胡散臭く感じるのは私だけではないと思います。それに功利主義は損得で判断するわけですが、人類全体にとっては得だとしても、個人的には損なことをする理由を功利主義は説明できていないような気がします。「人格に基づくアプローチ」に関しては、「目には目を」的な発想をしがちな私はネスのような人格者ではないので少々無理があります。「バランスに基づくアプローチ」はよく分からないからダメとなると、私に残されたのは「義務に基づくアプローチ」で、学生時代に生態学を学んだせいか「全体論」にシンパシーを感じるとなると、どうしても「全体論×義務に基づくアプローチ」になってしまいます。
ハンス・ヨナスのところで「定言命法」という言葉がでてきましたが、これと対になる概念として「仮言命法」というのがあります。「仮言命法」は「△△でありたいなら、○○せよ」というもので、結果を重視する「功利主義的アプローチ」の場合には常に何らかの条件付きで「○○せよ」(或いは「××してはならない」)と命じます。これに対し「定言命法」というのは条件無しに「○○せよ」と命じるもので、原則を重視する「義務に基づくアプローチ」はこのタイプになります。「救命ボート倫理」のハーディンの場合には、「全体論」ではありますが「功利主義的アプローチ」なので、条件によっては負傷者選別をしない可能性もあります。しかし、私の場合は「全体論×義務に基づくアプローチ」なので、もしかすると自分は何の留保もなしに正真正銘の「環境ファシスト」なのではないかという後ろめたさを伴った恐怖のようなものを感じていました。それが、アンビュルジェが個体論と全体論の対立を吹き飛ばしてくれたおかげで、ついに「環境ファシスト恐怖症」を抜け出すことができたのです。周りから見たら私は前から「お気楽」だったのかもしれませんが、近頃は以前にも増して安心して眠れるようになりました。
アンビュルジェは、人と自然の間の橋は燃やされたと言うことによって、架橋不可能と思われた個体論的倫理と全体論的倫理の間に橋を架けてしまったのです。
反逆者の誇り
人間はトム・レーガンの言うところの「本来価値を持つ生命体」の典型です。彼にしたがえば、「本来価値を持つ生命体は、他の目的のための手段としてのみ扱ってはならない」ということになります。私の勤める大学の基本理念には、「公立鳥取環境大学は、「人と社会と自然の共生」の実現に貢献する有為な人材の育成と創造的な研究を行うことを基本理念としています」と書かれています。揚げ足を取るようで何ですが、「材」という言葉は「役に立つべきもの」を意味しており、「人材」という言葉は「何らかの目的に役立つ手段としての人間」を意味します。残念ながら、大学の基本理念の中には、本来価値を持つ生命体としての学生の位置づけはありません。学生が社会の役に立ってはいけないということは全くないのですが、教育機関の理念としては、社会の役に立つか立たないか以前に、「それぞれの学生が自己実現を図れるよう、教育を通じてサポートする」というようなことが書かれていて然るべきかと思います。
第二次世界大戦中、ナチスドイツは600万人以上のユダヤ人を虐殺しましたが、その前に、精神障害者や知的障害者、回復の見込みのない病人など20万人以上をガス室に送るなどして秘密裏に殺していました。T4作戦と呼ばれ、障害者に「恵みの死を与える」と称して行われたこの安楽死計画の背後にあるのは、人間を国家(全体)の役に立つ人間と、役に立たない人間に分ける思想です。戦前の日本でも、人間は国家の利益のための手段と位置づけられていたのだと思います。私の勤める大学の基本理念は特別なものではなく、どこの大学の基本理念にも大抵は「有為な人材の育成」ということが書かれています。そうすると、国のため、会社のため、環境のためと目的は変わっても、人間を全体の利益のための手段として位置づける発想は今も当たり前のこととして残っていることになります。もしかすると、ナチズムと私たちの間には、そんなに大きな隔たりはないのかもしれません。これからはアンビュルジェの教えに従って、自然に反逆した種族の一員であることに誇りを持って自由、平等などの反自然的価値を尊重し、社会全体の利益や発展ではなく、個々の人間が自己実現できる社会を目指すという方向で持続可能社会を考えていきたいと思います。
アンビュルジェの思想のうち、同意できないとこがあるとすれば、それはアンビュルジェが現代社会の諸悪の根源として「人口爆発」を挙げていることです。確かに、有限の地球の上で無限に人口を増やすことはできなのですが、それ以上に問題なのが、成長なしには存続し得ない「資本主義」という経済の仕組だと思います。格差社会ということが言われるようになって暫く経ちますが、格差の拡大が貧しい人たちから教育の機会を奪い、それが自己実現の妨げになっているのだとしたら、それは自然に反逆した種族にとっては由々しいことです。
格差の是正に向けて二つのことを提案したいと思います。一つは「営利株式会社の廃止」で、もう一つは「相続制度の廃止」です。
営利株式会社の制度を廃止するのは、それが社会を経済成長という檻に閉じ込めている元凶であるのと同時に、CEOなどのエリート経営者と一般労働者の所得格差を生み出している元凶と思われるからです。株主が企業を所有する営利株式会社は廃止して、企業はワーカーズコープ(そこで働く人たちが所有)や消費者協同組合(サービスを受ける消費者が所有)という形態にすればよいのだと思います。
相続制度を廃止するのは、ピケティ氏によれば所得格差よりも資産格差の方が大きく、その資産格差が所得格差を生み出し、それが資産格差を拡大再生産しているからです。財産を相続できるのは配偶者までで、子供は親の財産を相続できないことにしてしまえば、資産格差に基づく格差拡大の問題は解消できるのではないでしょうか。フランスで子供が農場を引き継ぐときに、親から買い取っているというのをテレビで見たことがあります。子供が親の財産を引き継ぎたいときには、親から買い取る。そして、親はそのお金と年金で暮らしていく。それでよいのではないかと思うのですが、読者の皆さんはどうお考えになるでしょうか。この場合、子供が買い取らなかった財産は政府が没収することになります。財産は基本的には生活の糧を得るための手段であるはずなので、生きている人から財産を奪うことは人権の侵害になるでしょう。しかし、死んだ人の財産を没収しても人権の侵害にはならないと思います。
おわりに
祖先が自然と離婚して橋を燃やしたのはいつのことなのでしょうか。クストーと本の編著者である服部英二氏の対話によれば、それは人類が言葉を手に入れたときで、そのとき人は言葉と共に理性(ロゴス)を手に入れたというのです。確かに、言葉なしに「自由」や「平等」などの概念をある程度固定されたものとして保持するのは困難な気がするので、もっともだと思います。言葉を手に入れて概念操作が出来るようになると、人は遺伝子ではなく、大脳の指令に従って生きるようになったのかもしれません。では、その時期はということなのですが、それは7万5000年前頃のようです。本では、次のような服部氏と言語学者のノーム・チョムスキーの対話も紹介されています。
チョムスキー:言葉は、今から5万から10万年前(中間をとるなら7万5千年前)、突如として人類に与えられた。それは最初から最適なデザインを持ち、普遍的文法があった。その現れ方は、まるで空中に結晶として雪片が現れるのに似ていた。
服部:あなたのいう言葉の出現は人類の出アフリカの時期と一致するのではないか?
チョムスキー:あなたの指摘は非常に面白い。
ここで服部氏が示唆している説に従うと、ホモ・サピエンスは自然と離婚してからアフリカを出て、地球の表面を人間向きに改造しながら世界に拡がっていったことになります。この地球改造が20世紀の後半になって限界に達し、私たちは今、路線変更を迫られている。そういうことになります。ホモ・サピエンスの登場は約20万年前とのことですが、言葉を手に入れる前は単なる「裸のサル」で、言葉を手に入れてから本当の意味での「人間」になったとすると、反逆者であることが人間の本性ということでしょうか。灌漑農業を基盤とする都市文明に始まる人間圏の出現は、地球史的には画期的な出来事だったのでしょうが、人類史的には、それは反逆者が本領を発揮し始めたに過ぎないことになります。フロンティアが無くなった今、アフリカから始まったホモ・サピエンスの旅は終わりを迎えたのでしょうか、それともやはり宇宙へと向かうのでしょうか。それを考えると、最後のフロンティアがあったアメリカが宇宙開発の中心地となっているのは、何だか意味深な気がします。宇宙に向かった人類が帰ってきたとき、青い地球を見ることはできるのでしょうか。
◇
前回このメールニュースに書かせて頂いた時は「進歩と救い」ということで、あまり「環境」とは関係ないテーマでした。今回は「環境」には関係あったのですが、かなり個人的な話になってしまったことをお許し頂ければと思います。長い文章にお付き合いいただき、ありがとうございました。
追記
私は時々、アイゼンハワーの離任演説を読み返しています。理由はそこに「バランスに基づくアプローチ」の核心が秘められているような気がするからです。インターネットで原文と音声、および豊島幸一氏による日本語訳が公開されています。関心のある方は下記をご覧ください。
原文と音声:
http://www.americanrhetoric.com/speeches/dwightdeisenhowerfarewell.html
日本語訳:
http://ad9.org/pegasus/kb/EisenhowerAddress.html
参考文献
- ヨハン・ホイジンガ:朝の影のなかに,中公文庫,1984.
- アルド・レオポルド:野生のうたが聞こえる,講談社学術文庫,1997.
- ジョゼフ・R・デ・ジャルダン:環境倫理学―環境哲学入門,人間の科学社,2008.
- 同上
- アルネ・ネス:自己実現―この世界におけるエコロジカルな人間存在のあり方,アラン・ドレングソン,井上有一(共編):ディープ・エコロジー 生き方から考える環境の思想,昭和堂,2003所収.
- 同上
- ハンス・ヨナス:責任という原理―科学技術文明のための倫理学の試み(新装版),東信社,2010.
- 服部英二(編著):未来世代の権利 地球倫理の先覚者、J-Y・クストー,藤原書店,2015.
(あらた てつじ:KIESS事務局長・鳥取環境大学准教授)
◇◇◇◇◇◇◇◇
KIESS MailNews は3ヶ月に1度、会員の皆様にメールでお送りしている活動情報誌です。
KIESS会員になっていただくと、最新のMailNewsをいち早くご覧いただくことができ、2ヶ月に1度の勉強会「KIESS土曜倶楽部」の講演要旨やイベント活動報告など、Webサイトでは公開していない情報も入手できるほか、ご自身の活動・研究の紹介の場としてMailNewsに投稿していただくこともできるようになります。
詳しくは「入会案内」をご覧ください。
